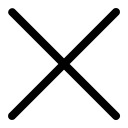ゼポジア® (オザニモド) 添付文書
ゼポジア® (オザニモド) 添付文書
A スターターパックに含まれるカプセル(0.23mgカプセル及び0.46mgカプセル)と0.92mgカプセルの生物学的同等性は示されておりません。[1] このため、0.92mgカプセルの代わりにスターターパックに含まれるカプセルを使用する事はできません。投与時期に合ったカプセルを使用するようお願いします。
<添付文書>
7. 用法及び用量に関連する注意
7.6 スターターパックに含まれるカプセル(0.23mgカプセル及び0.46mgカプセル)と0.92mgカプセルの生物学的同等性は示されていないため、1~7日目はスターターパック、8日目以降は0.92mgカプセルを使用し、互換使用を行わないこと。
A 乾燥弱毒性麻しんワクチン、乾燥弱毒性風しんワクチン、乾燥BCG等の生ワクチンは、併用禁忌として規定されています。本剤は免疫系に抑制的に作用するため、本剤投与中に生ワクチンを接種すると病原性をあらわし発症するおそれがあります。本剤の投与中及び投与終了後最低3ヵ月間は、生ワクチンの接種を避けてください。また、生ワクチンによる免疫獲得が必要な場合は、本剤投与開始1ヵ月以上前に接種するようお願いします。[1]
<添付文書>
A 経口5-アミノサリチル酸製剤又はステロイドの投与歴がある中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象とした国内第Ⅱ/Ⅲ相試験において発現した主な副作用は、オザニモド0.46mg群でγ-GTP増加5.9%(4/68例)、頭痛2.9%(2/68例)及び肝機能検査値上昇2.9%(2/68例)、オザニモド0.92mg群でALT増加4.6%(3/65例)、帯状疱疹3.1%(2/65例)、回転性めまい3.1%(2/65例)、肝機能異常3.1%(2/65例)、γ-GTP増加3.1%(2/65例)、AST増加3.1%(2/65例)及び肝機能検査値上昇3.1%(2/65例)でした。[1]
A ゼポジアの投与開始前に12誘導心電図により心伝導異常の有無を確認し、本剤の投与の可否を慎重にご検討ください。電子化された添付文書(電子添文)上、心拍数低下、心伝導異常、不整脈等を含む心疾患(禁忌対象を除く)のリスクを有する患者又はこれらのリスクを有する薬剤を投与中の患者に本剤を投与する場合、投与開始前に12誘導心電図及びバイタルサインを測定し、初回投与後6時間は継続してバイタルサインの測定を行うこと。投与から6時間経過後に12誘導心電図を測定し、異常が認められる場合には、12誘導心電図及びバイタルサインの測定を継続することが規定されています。[1][3]
<添付文書>
8. 重要な基本的注意
8.1 心拍数低本剤の投与開始前に12誘導心電図により心伝導異常の有無を確認し、本剤の投与の可否を慎重に検討すること。下、房室伝導の遅延が生じることがあるため、以下に注意すること。
8.1.1 本剤の投与開始前に12誘導心電図により心伝導異常の有無を確認し、本剤の投与の可否を慎重に検討すること。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 心拍数低下、心伝導異常、不整脈等を含む心疾患(禁忌対象を除く)のリスクを有する患者又はこれらのリスクを有する薬剤を投与中の患者
本剤投与による有益性と危険性を考慮した上で、投与の可否を慎重に検討すること。本剤の投与を考慮する場合には、本剤の投与開始前に12誘導心電図及びバイタルサインを測定し、初回投与後6時間は継続してバイタルサインの測定を行うこと。投与から6時間経過後に12誘導心電図を測定し、異常が認められる場合には、12誘導心電図及びバイタルサインの測定を継続すること。また、初回投与後の患者の状態に応じて、漸増期間中も12誘導心電図及びバイタルサインを測定することを検討すること。なお、本剤を休薬し、再度漸増を行う場合も、同様の測定を行うこと。本剤の投与により心拍数低下、房室伝導の遅延が生じることがあり、特に本剤の漸増期間中に生じる可能性が高い。
A 電子化された添付文書(電子添文)上、黄斑浮腫の既往又は黄斑浮腫のリスク因子(ブドウ膜炎又は糖尿病の既往歴等)を有する患者においては、本剤投与開始前に眼底検査を含む眼科学的検査を実施し、投与中にも定期的な眼科学的検査を実施することが規定されています。[1] 黄斑浮腫の既往またはリスク因子を有さない場合でも、本剤投与中に黄斑浮腫があらわれることがあるため、本剤投与中は眼底検査を含む定期的な眼科学的検査を実施することが規定されています。特に、患者が視覚障害を訴えるなど異常が認められた場合は、眼科学的検査を実施してください。[1]
<添付文書>
8. 重要な基本的注意
8.6 黄斑浮腫があらわれることがあるため、本剤投与中は眼底検査を含む定期的な眼科学的検査を実施すること。患者が視覚障害を訴えた場合にも眼科学的検査を実施すること。
9.特定の背景を有する患者に関する注意
9.1合併症・既往歴等のある患者
9.1.3黄斑浮腫の既往又は黄斑浮腫のリスク因子(ブドウ膜炎又は糖尿病の既往歴等)を有する患者
本剤投与開始前に眼底検査を含む眼科学的検査を実施し、投与中にも定期的な眼科学的検査を実施すること。
11.副作用
11.1 重大な副作用
11.1.3 黄斑浮腫(0.6%)
異常が認められた場合には眼科学的検査を実施すること。黄斑浮腫が確認された場合には、本剤の投与を中止すること。
A 本剤の薬理作用により循環血中のリンパ球数が減少します。本剤投与開始後、リンパ球数が200/mm3未満となった場合には本剤の投与を中断して、患者の状態を慎重に観察し、感染症の徴候にご注意ください。投与再開は、リンパ球数500/mm3以上を目安とし、治療上の有益性と危険性を慎重に評価した上で投与再開の是非についてご判断いただきますようお願いします。[1]
<添付文書>
8.重要な基本的注意
8.4本剤の薬理作用により循環血中のリンパ球数が減少するため、本剤投与開始前に血液検査(血球数算定等)を行うとともに、投与中には定期的に血液検査(血球数算定等)を行うこと。本剤投与開始後、リンパ球数が200/mm3未満となった場合には投与を中断して、患者の状態を慎重に観察し、感染症の徴候に注意すること。投与再開は、リンパ球数500/mm3以上を目安とし、治療上の有益性と危険性を慎重に評価した上で判断すること。
A ゼポジアを妊婦に投与する事は、禁忌に該当します。妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、本剤を投与しないでください。[1]
<添付文書>
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
2.7 妊婦又は妊娠している可能性のある女性
9.特定の背景を有する患者に関する注意
9.5妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。ウサギにおいて、オザニモドの臨床曝露量の5倍以上の曝露量で、胚・胎児死亡、骨化遅延、並びに大血管及び骨格の異常が認められている。
A ゼポジアを服用中の方は、授乳しないことが望ましいです。[1] なお、電子化された添付文書では、下記の通り注意喚起しています。
<添付文書>
9.特定の背景を有する患者に関する注意
9.6 授乳婦
授乳しないことが望ましい。ヒト乳汁中への本剤の移行、授乳児への影響及び乳汁産生への影響に関するデータはないが、ラットで本剤及びその代謝物が乳汁中へ移行することが認められている。
A 電子化された添付文書上、投与対象者に年齢の上限は設けられておりませんが、下記の通り注意喚起しています。[1] 一般的に高齢者では生理機能が低下しているため、投与に際しては、患者の状態を十分に観察し、リスクとベネフィットを十分に考慮した上で慎重にご投与いただきますようよろしくお願いいたします。
<添付文書>
9.特定の背景を有する患者に関する注意
9.8 高齢者
患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。一般に高齢者では、生理機能が低下している。
A 電子化された添付文書上、腎機能障害のある患者への投与に関し規定は設けられておりませんが、以下の通り記載しております。[1]
投与に際しては、患者の状態を十分に観察し、リスクとベネフィットを十分に考慮した上で、医師の判断でお願いします。
<添付文書>
16.6 特定の背景を有する患者
16.6.1 腎機能障害患者
末期腎不全(ESRD)の被験者(8例)及び腎機能正常被験者(8例)にオザニモド0.23mgを単回経口投与したとき、腎機能障害がオザニモド及びCC112273の薬物動態に及ぼす影響は下表のとおりであった(外国人データ)。
A 電子化された添付文書上、透析中の患者への投与に関し規定は設けられておりません。ゼポジアの投与に際しては、患者の状態を十分に観察し、リスクとベネフィットを十分に考慮した上で、医師の判断でお願いします。
なお、添付文書上の腎機能障害患者に対する注意喚起は以下の通りです。[1]
<添付文書>
16.6 特定の背景を有する患者
16.6.1 腎機能障害患者
末期腎不全(ESRD)の被験者(8例)及び腎機能正常被験者(8例)にオザニモド0.23mgを単回経口投与したとき、腎機能障害がオザニモド及びCC112273の薬物動態に及ぼす影響は下表のとおりであった(外国人データ)。
A ヒトでのデータはありませんが、非臨床試験において、オザニモド投与による肺の変化は、反復投与毒性試験及びがん原性試験の各動物種で一貫して、肺重量増加並びに肺胞マクロファージ集簇及び肺組織球症の発現頻度の増加が認められましたが、これらの変化の発現頻度及び程度は投与期間に伴って増加せず、回復性が認められました。[3] これに伴い、電子化された添付文書上、下記の通り注意喚起しています。[1]
重度の呼吸器疾患を有する患者にゼポジアを投与する場合、症状が増悪するおそれがあります。呼吸器疾患のある患者にゼポジアを投与される場合には、患者の状態を十分に観察するなど、慎重にご投与いただきますようお願いします。
<添付文書>
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.4 重度の呼吸器疾患を有する患者
症状が増悪するおそれがある。
15. その他の注意
15.2 非臨床試験に基づく情報
ラット及びサルを用いた一般毒性試験において、肺重量の増加及び肺胞の単核細胞浸潤の発現率の増加が認められた。
ゼポジアの投与8日目以降は、維持用量である「0.92mgカプセル」を処方してください。
投与開始1~7日目はスターターパック、8日目以降は0.92mgカプセルを使用し、互換使用しないでください。[3]
A 本剤の服用を忘れた場合、気づいたのが当日中であれば、気づいた時点で直ちに1回分を服用し、同じ日に2回分を服用しないようにご注意ください。もし、前日飲み忘れたことに翌日気づいた場合は、飲み忘れた分は1回飛ばし、下図の通り翌日の服用予定時刻に1回分の服用量を服用してください。[3]
また、以下①~➂の様にゼポジアを休薬または飲み忘れた場合は、開始用量である0.23mgから投与を再開し、用法及び用量のとおり漸増してください。[3]
① 投与開始後14日以内に1日以上の休薬
② 投与開始後15~28日の間に7日間を超えて連続して休薬
③ 投与開始後28日を経過した後に14日間を超えて連続して休薬
休薬期間が上記より短い場合は、次に予定された用量で投与を継続してください。[3]
A ゼポジアの投与により心拍数の低下がみられ、特に本剤の漸増期間中に生じる可能性が高いことから、循環器を専門とする医師と連携するなど、適切な処置が行える管理下で本剤の投与を開始してください。[3]
また、下記の様な心拍数低下リスクを有する患者またはこれらのリスクを有する薬剤を投与中の患者にゼポジアを投与する場合には、本剤投与による有益性と危険性を考慮した上で、投与の可否を慎重に検討してください。[3]
本剤の投与を考慮する場合には、本剤の投与開始前に12誘導心電図及びバイタルサインを測定し、初回投与後6時間は継続してバイタルサインの測定を行ってください。投与から6時間経過後に12誘導心電図を測定し、異常が認められる場合には、12誘導心電図及びバイタルサインの測定を継続してください。また、初回投与後の患者の状態に応じて、漸増期間中も12誘導心電図及びバイタルサインを測定することを検討してください。
なお、本剤を休薬し、再度漸増を行う場合も、同様の測定を行ってください。
本剤の投与により心拍数低下、房室伝導の遅延が生じることがあり、特に本剤の漸増期間中に生じる可能性が高くなります。[3]
≪心拍数低下リスクを有する患者またはこれらのリスクを有する薬剤を投与中の患者≫
●心拍数低下、心伝導異常、不整脈等を含む心疾患(禁忌対象を除く)のリスクを有する患者
(例)
・本剤の投与開始前6ヵ月より前に心筋梗塞、不安定狭心症、脳卒中、一過性脳虚血発作、入院を要する非代償性心不全、NYHA分類Ⅲ度又はⅣ度の心不全を発症した患者
・ペースメーカーを使用しているモビッツⅡ型第2度房室ブロック、第3度房室ブロック又は洞不全症候群の既往歴又は合併症のある患者
・著しいQT延長(男性:QTcF値450msec 超、 女性:QTcF値470msec 超)が認められる患者
●心拍数低下、心伝導異常、不整脈等のリスクを有する薬剤を投与中の患者
(例)
・QT延長作用のある薬剤
・クラスⅠa抗不整脈剤(キニジン、プロカインアミド等)、クラスⅢ抗不整脈剤(アミオダロン、ソタロール等)
・心拍数を低下させる可能性のある薬剤(ジゴキシン等)・β遮断剤(プロプラノロール等)、カルシウムチャネル拮抗剤(ジルチアゼム等)
A 国内外の臨床試験及び海外の製造販売後において、ゼポジア投与により黄斑浮腫が報告されており、黄斑浮腫のリスク因子を伴わない症例も報告されています。[3]
特に、黄斑浮腫の既往のある患者、またはブドウ膜炎又は糖尿病の既往歴等の黄斑浮腫のリスク因子のある患者へ本剤を投与する際はご注意ください。
A 非臨床試験において、オザニモド投与による肺の変化は、反復投与毒性試験及びがん原性試験の各動物種で一貫して、肺重量増加並びに肺胞マクロファージ集簇及び肺組織球症の発現頻度の増加が認められましたが、これらの変化の発現頻度及び程度は投与期間に伴って増加せず、回復性が認められました。[3]