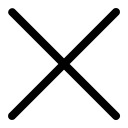レブロジル® (ルスパテルセプト) 添付文書
レブロジル® (ルスパテルセプト) 添付文書
A
適正使用ガイドP12「4. 注意を要する副作用とその対策(1)造血器悪性腫瘍」より1。
MedDRA(ver25.0)
Grade判定は、NCI CTCAE規準に基づく(ver4.03)
※ 治験薬の投与開始以降、最終投与日から42日後までに発現した治験薬との関連性が疑われる有害事象及び、以降時期を問わず発現した治験薬との関連性が疑われる重篤な有害事象
MedDRA(ver25.0)
Grade判定は、NCI CTCAE規準に基づく(ver4.03)
※ 治験薬の投与開始以降、最終投与日から42日後までに発現した治験薬との関連性が疑われる有害事象及び、以降時期を問わず発現した治験薬との関連性が疑われる重篤な有害事象
MedDRA(ver23.0)
Grade判定は、NCI CTCAE規準に基づく(ver4.0)
※ 治験薬の投与開始以降、最終投与日から42日後までに発現した治験薬との関連性が疑われる有害事象
別添
赤血球輸血依存注6)で、赤血球造血刺激因子製剤に対して不応、不耐容又は不適格で、RS陽性注7)の、IPSS-Rによるリスク分類のVery low、Low又はIntermediateに分類される骨髄異形成症候群注8)[WHO分類改訂第4版(2017年)において定義される環状鉄芽球と血小板増加を伴う骨髄異形成/骨髄増殖性腫瘍に該当する患者を含む]患者229例を対象に、プラセボを対照として、本剤の有効性及び安全性を検討した。本剤1.0mg/kg又はプラセボを3週間間隔で皮下投与し、赤血球輸血量の変化注9)等に基づいて0.45~1.75mg/kgの3週間間隔投与の範囲で調節可能とした注10)。主要評価項目である24週間以内に連続8週間以上の赤血球輸血非依存(赤血球輸血を必要としない状態)を達成した患者の割合[95%信頼区間]は、本剤群で37.9%[30.2,46.1](58/153例)、プラセボ群で13.2%[6.5, 22.9](10/76例)であり、本剤はプラセボに対して統計学的に有意な改善を示した[共通リスク差(95%信頼区間)24.6(14.5, 34.6)、p<0.0001(Cochran-Mantel-Haenszel検定)](2018年5月8日データカットオフ)。
副作用発現頻度は、本剤群で46.4%(71/153例)であった。主な副作用は、悪心7.2%(11/153例)、疲労5.9%(9/153例)、筋肉痛5.2%(8/153例)、頭痛4.6%(7/153例)、ALT増加3.9%(6/153例)及び下痢3.3%(5/153例)であった。[5.2参照]
注6)無作為化前16週間において、①平均赤血球輸血量が8週間あたり2単位以上、②連続8週間無輸血の期間がないこと、及び③赤血球輸血前7日以内のヘモグロビン濃度が10.0g/dL以下を満たす患者を対象とした。
注7)骨髄中のRSが赤血球前駆細胞の15%以上(ただし、SF3B1遺伝子変異を有する場合は骨髄中のRSが赤血球前駆細胞の5%以上)の場合をRS陽性、それ以外の場合をRS陰性と定義した。
注8)5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群患者は除外した。
注9)直近の6週間で1単位以上の赤血球輸血を実施した場合等は増量し、ヘモグロビン濃度が11.5g/dL以上の場合は、11g/dL以下になるまで休薬、ヘモグロビン濃度が3週間で2g/dL以上の上昇を認めた場合等は減量した。
注10)増量は2回目投与以降に実施可能とし、1.33、1.75mg/kgの順で漸増することとした。
試験結果の詳細についてはインタビューフォームP29 「V. 5. (4). 海外第Ⅲ相試験(ACE-536-MDS-001:MEDALIST)」[2]もご参照ください。
赤血球輸血依存注6)で、赤血球造血刺激因子製剤に対して不応、不耐容又は不適格で、RS陽性注7)の、IPSS-Rによるリスク分類のVery low、Low又はIntermediateに分類される骨髄異形成症候群注8)[WHO分類改訂第4版(2017年)において定義される環状鉄芽球と血小板増加を伴う骨髄異形成/骨髄増殖性腫瘍に該当する患者を含む]患者229例を対象に、プラセボを対照として、本剤の有効性及び安全性を検討した。本剤1.0mg/kg又はプラセボを3週間間隔で皮下投与し、赤血球輸血量の変化注9)等に基づいて0.45~1.75mg/kgの3週間間隔投与の範囲で調節可能とした注10)。主要評価項目である24週間以内に連続8週間以上の赤血球輸血非依存(赤血球輸血を必要としない状態)を達成した患者の割合[95%信頼区間]は、本剤群で37.9%[30.2,46.1](58/153例)、プラセボ群で13.2%[6.5, 22.9](10/76例)であり、本剤はプラセボに対して統計学的に有意な改善を示した[共通リスク差(95%信頼区間)24.6(14.5, 34.6)、p<0.0001(Cochran-Mantel-Haenszel検定)](2018年5月8日データカットオフ)。
副作用発現頻度は、本剤群で46.4%(71/153例)であった。主な副作用は、悪心7.2%(11/153例)、疲労5.9%(9/153例)、筋肉痛5.2%(8/153例)、頭痛4.6%(7/153例)、ALT増加3.9%(6/153例)及び下痢3.3%(5/153例)であった。[5.2参照]
注6)無作為化前16週間において、①平均赤血球輸血量が8週間あたり2単位以上、②連続8週間無輸血の期間がないこと、及び③赤血球輸血前7日以内のヘモグロビン濃度が10.0g/dL以下を満たす患者を対象とした。
注7)骨髄中のRSが赤血球前駆細胞の15%以上(ただし、SF3B1遺伝子変異を有する場合は骨髄中のRSが赤血球前駆細胞の5%以上)の場合をRS陽性、それ以外の場合をRS陰性と定義した。
注8)5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群患者は除外した。
注9)直近の6週間で1単位以上の赤血球輸血を実施した場合等は増量し、ヘモグロビン濃度が11.5g/dL以上の場合は、11g/dL以下になるまで休薬、ヘモグロビン濃度が3週間で2g/dL以上の上昇を認めた場合等は減量した。
注10)増量は2回目投与以降に実施可能とし、1.33、1.75mg/kgの順で漸増することとした。
試験結果の詳細についてはインタビューフォームP29 「V. 5. (4). 海外第Ⅲ相試験(ACE-536-MDS-001:MEDALIST)」[2]もご参照ください。
溶解後やむを得ず保存する場合は、常温又は2~8℃で保存し、常温で保存する場合は8時間以内、2~8℃で保存する場合は24時間以内に使用すること。2~8℃で保存する場合、投与の15~30分前に冷蔵庫から取り出し、室温に戻す。溶解液は凍結させないこと。
A
インタビューフォーム「有効成分の各種条件下における安定性」より2。
A
電子添文「9. 特定の背景を有する患者に関する注意」3及び
適正使用ガイドP7. 「2. (3)特定の背景を有する患者に関する注意」1より。
適正使用ガイドP15. 「5. Q5. 本剤投与終了後、どのくらいの期間避妊する必要がありますか?」より1。
インタビューフォームP66~ 「海外における臨床支援情報」より2。
A
電子添文「5. 効能又は効果に関連する注意」より3。
5.1 IPSS-R注)によるリスク分類のHigh及びVery Highに対する有効性及び安全性は確立していない。
注)Revised International Prognostic Scoring System(国際予後スコアリングシステム改訂版)
A
適正使用ガイドP14「Q3. エリスロポエチン濃度が500U/L以上の患者での有効性は?」より1。
A
電子添文「7. 用法及び用量に関連する注意」より3。
7.2 本剤1.75mg/kgを3回(9週間)投与した時点を目安として、輸血量の減少やヘモグロビン濃度の上昇等の効果が認められない場合には、本剤の投与継続の要否を検討すること。
A
インタビューフォーム P28「V. 5. (4) 〈国際共同第Ⅲ相試験(ACE-536-MDS-002:COMMANDS)〉」より2。
試験の対象:赤血球輸血依存*1で、赤血球造血刺激因子製剤の治療歴がなく、環状鉄芽球陽性又は陰性を問わない、IPSS-Rによるリスク分類のVery low、Low又はIntermediateに分類される骨髄異形成症候群(環状鉄芽球と血小板増加を伴う骨髄異形成/骨髄増殖性腫瘍を含む)患者356例(日本人患者20例を含む)
*1:無作為化前8週間の赤血球輸血量が2~6単位の患者を対象とした。なお、当該赤血球輸血は、赤血球輸血時又は輸血実施前7日以内のヘモグロビン濃度が9.0g/dL以下(貧血症状がある場合)又はヘモグロビン濃度が7.0g/dL以下(貧血症状がない場合)でなければならないとした。また、無作為化前の最後の赤血球輸血実施後のヘモグロビン濃度が11.0g/dL未満の患者を対象とした。
A
インタビューフォームP24 「V. 5. (4) 〈国内第Ⅱ相試験(ACE-536-MDS-003)>主要評価項目」2より。
主要評価項目:24週以内にIWG基準(2006)に基づく血液学的改善-赤血球反応*[7]を達成した患者割合
*7:赤血球輸血を受けることなく、いずれかの時点で連続56日間にわたりヘモグロビン濃度の1.5g/dL以上の上昇を達成した患者割合
参考文献
A
製品情報について検索する場合は「Medical Information library(https://www.bmsmedinfo.jp/)」をご利用ください。
製品に関して問い合わせをする場合は、「製品に関するお問い合わせ(https://www.bmsmedinfo.jp/submit-medical-inquiry.html)」ページをご利用ください。
REFERENCES