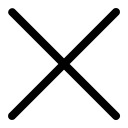オータイロ® (レポトレクチニブ) 添付文書
オータイロ® (レポトレクチニブ) 添付文書
A オータイロを脱カプセルして投与した場合の有効性及び安全性は検討されていません。
カプセルは開けたり、つぶしたり、噛んだり、内容物を溶かしたりせず、そのまま投与してください。[3]
A ROS1、NTRK又はALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌患者を対象とした国際共同第I/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅰ相パートにおける用量制限毒性、最大耐量及び予備的な有効性解析の結果、及び薬物動態/薬力学の統合解析によるシミュレーションの結果から、オータイロの第Ⅱ相試験の推奨用量を最初の14日間は1回160mg 1日1回とし、特定の基準(Grade 3以上の治験薬と関連のある有害事象、管理不能のGrade 2以上の浮動性めまい、運動失調若しくは錯感覚、又はGrade3以上の臨床的に重要な臨床検査値異常が認められない)を全て満たしていれば、1回160mg 1日2回に増量可能と設定しました。
第Ⅱ相試験の推奨用量を投与した第Ⅱ相パートでは、ROS1チロシンキナーゼ阻害剤未治療及び既治療のROS1融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌患者及び、TRKチロシンキナーゼ阻害剤未治療及び既治療のNTRK融合遺伝子陽性の固形癌患者に対して高い奏効率及び持続的な抗腫瘍効果が示されました。オータイロを投与した患者で報告された有害事象はおおむね管理可能であり、オータイロは忍容可能な安全性プロファイルを示しました。
以上より、ROS1融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌患者及びNTRK融合遺伝子陽性の固形癌を有する成人患者に対するオータイロの用法及び用量として、オータイロ1回160mg 1日1回で14日間投与後、1回160mg 1日2回で投与(患者の状態により適宜減量)と設定しました。[2]
また、25歳以下のROS1、NTRK又はALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌患者を対象とした海外第I/Ⅱ相試験(CARE試験)の第Ⅰ相パートでは、12歳未満の患者を組み入れ、この年齢群での第Ⅱ相試験の推奨用量を決定した後、25歳以下の全ての被験者を第Ⅱ相パートに組み入れました。
第Ⅰ相パートで得られた予備的な安全性所見、臨床的ベネフィット及び薬物動態曝露量に基づき、小児患者におけるオータイロの第Ⅱ相試験の推奨用量を最初の14日間は1回160mg 1日1回(成人換算用量)とし、その後は特定の基準(Grade 3以上の治験薬と関連のある有害事象、管理不能のGrade 2以上の浮動性めまい、運動失調若しくは錯感覚、又はGrade 3以上の臨床的に重要な臨床検査値異常が認められない)を全て満たしていれば、1回160mg 1日2回(成人換算用量)に増量可能と設定しました。
第Ⅱ相試験の推奨用量を投与したCARE試験では、TRIDENT-1試験の成人患者と同様の臨床的ベネフィットが認められました。また、オータイロを投与した患者で報告された有害事象はおおむね管理可能であり、オータイロは忍容可能な安全性プロファイルを示しました。
以上より、NTRK融合遺伝子陽性の固形癌を有する4歳以上の小児患者に対するレポトレクチニブの用法及び用量として、体重30 kg以上の場合には1回160 mg、体重30 kg未満の場合には1回120 mgを1日1回14日間投与後、1日2回で投与(患者の状態により適宜減量)と設定しました。[2]
A オータイロの電子化された添付文書(電子添文)の副作用が発現した場合の減量規定は、国際共同第I/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅱ相パートの規定に準じ設定しました。[3]
オータイロの用量調整は、1段階減量として、投与量が1回160mg 1日2回の場合には1回120mg 1日2回へ、必要に応じて2段階減量として1回80mg 1日2回への変更を推奨しています。[3]
オータイロ 電子添文[1]
7. 用法及び用量に関連する注意
7.3 本剤投与により副作用が発現した場合には、以下の基準を参考に、本剤を休薬、減量又は中止すること。
オータイロの曝露反応解析の結果、1回120mg 1日2回に減量した集団及び1回160mg 1日1回に減量した集団の客観的奏効の達成確率は、チロシンキナーゼ阻害剤未治療例で80% vs 76%、チロシンキナーゼ阻害剤既治療例で38% vs 33%であり、1回120mg 1日2回に減量した集団は1回160mg 1日1回に減量した集団よりも高い客観的奏効の達成確率を示すと予測されました。同様に、1回120mg 1日2回の方が1回160mg 1日1回よりも無増悪生存期間を延長すると予測されました。[3]
QD:1日1回、BID:1日2回
TRIDENT-1試験の第Ⅱ相パートにおいて、オータイロを投与開始後1回160mg 1日2回に増量し、その後減量した患者のうち、1日2回の用法で減量した集団(69例)と1日1回の用法で減量した集団(23例)における有害事象の発現例数及び投与継続期間は以下のとおりでした。[3]
QD:1日1回、BID:1日2回
A オータイロの電子化された添付文書(電子添文)の副作用が発現した場合の減量規定は、国際共同第I/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅱ相パートの規定に準じ設定しました。[3]
オータイロの用量調整は、1段階減量として、投与量が1回160mg 1日2回の場合には1回120mg 1日2回へ、必要に応じて2段階減量として1回80mg 1日2回への変更を推奨しています。[3]
オータイロ 電子添文[1]
7. 用法及び用量に関連する注意
7.3 本剤投与により副作用が発現した場合には、以下の基準を参考に、本剤を休薬、減量又は中止すること。
臨床アウトカムの改善を伴う最適なベネフィット・リスクプロファイルを確保するためには、1日1回の投与頻度への減量(総投与量の50%の減量)よりも1日投与量の25%の減量で1日2回の投与頻度を維持することが推奨されます。1回160mg 1日1回への減量と比較して、1回120mg 1日2回への減量により曝露量の急激な減少が避けられました。
したがって、減量する場合には、電子添文のとおり1段階減量として、投与量が1回160mg 1日2回の場合には1回120mg 1日2回へ、必要に応じて2段階減量として1回80mg 1日2回への減量を推奨します。[3]
A オータイロの電子化された添付文書(電子添文)上、1日1回又は1日2回の用法いずれにおいても、オータイロの服用タイミグについては規定されていません。毎日なるべく同じ時間帯に服用するよう患者に指導してください。[1]
オータイロの電子添文上の用法及び用量は以下のとおりです。[1]
6. 用法及び用量
〈ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉
通常、成人にはレポトレクチニブとして1回160mgを1日1回14日間経口投与する。その後、1回160mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。
〈NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌〉
通常、レポトレクチニブとして以下の用量を1日1回14日間経口投与する。その後、同用量を1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。
・成人には、1回160mg
・4歳以上の小児には、体重に合わせて次の用量
A オータイロは、食前・食後のいずれのタイミングでも服用可能です。[1][3]
健康成人男性(14例)にオータイロ160mgを食後(高脂肪、高カロリー食)に単回経口投与したとき、空腹時(10時間絶食後)投与と比較してオータイロのCmax及びAUCinfの幾何平均値比はそれぞれ2.49及び1.56でした(外国人データ)。しかし、ROS1、NTRK又はALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌患者を対象とした国際共同第I/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)においては、用量標準化したCmax及びAUCinfの幾何平均値比(食後投与/1時間絶食後)はそれぞれ1.15及び1.23でした。食事による影響はわずかであり、その差は固形癌患者の個体間変動の範囲内でした。[1][2][3]
また、母集団薬物動態シミュレーションの結果、定常状態では単回投与と比較して食事の影響は低下することが示されています。[3]
A 飲み忘れた場合は、決して2回分を一度に服用しないこと、気が付いたときに1回分を服用すること、ただし、次の服用時間が近い場合は1回とばして、次の時間に服用することを患者に指導してください。
なお、国際共同第I/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅱ相パートでは、1日1回の投与間隔は約24時間(±2時間)とされ、12時間を超えて遅延した場合は投与をスキップしました。同様に、1日2回の投与間隔は約12時間(±1時間)とされ、6時間を超えて遅延した場合は投与をスキップしました。[3]
A ROS1、NTRK又はALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌患者を対象とした国際共同第I/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅱ相パートで発現した主な副作用は以下のとおりでした。[1]
ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者(2022年12月19日データカットオフ)
浮動性めまい57.7%(180/312例)、味覚不全48.7%(152/312例)、錯感覚30.4%(95/312例)、便秘26.3%(82/312例)、貧血25.3%(79/312例)、運動失調20.2%(63/312例)
NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌患者(2023年10月15日データカットオフ)
浮動性めまい59.3%(80/135例)、味覚不全54.8%(74/135例)、貧血31.9%(43/135例)、錯感覚30.4%(41/135例)、便秘28.9%(39/135例)、運動失調23.0%(31/135例)、疲労20.7%(28/135例)
また、25歳以下のROS1、NTRK又はALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌患者を対象とした海外第I/Ⅱ相試験(CARE試験)で発現した主な副作用は、疲労31.6%(6/19例)、貧血、味覚不全及び白血球数減少各26.3%(5/19例)、体重増加及び錯感覚各21.1%(4/19例)でした。[1]
A オータイロの電子化された添付文書(電子添文)上、中枢神経系障害(めまい・運動失調・認知障害等)は重大な副作用に該当します。オータイロの投与により中枢神経系障害が発現した場合には、電子添文の基準を参考に、オータイロを休薬、減量又は中止してください。[1]
また、めまい、運動失調、認知障害等の中枢神経系の副作用が認められた場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作を避けるよう患者へ指導してください。[1]
オータイロは、ROS1の他、トロポミオシン受容体キナーゼであるTRKA、TRKB及びTRKCを阻害することが、in vitro及びin vivoで示されています。TRKは感覚ニューロンの発生と分化において重要な役割を果たすことが知られており、TRK阻害に起因する有害事象は、固有感覚の低下及び小脳機能障害と関連していると考えられています。[3]
めまい、運動失調、認知障害には、以下の疾患が含まれます。[3]
めまい:浮動性めまい、回転性めまい、労作性めまい、体位性めまい、頭位性回転性めまい
運動失調:運動失調、歩行障害、平衡障害、小脳性運動失調、協調運動異常、眼振
認知障害:記憶障害、注意力障害、認知障害、注意欠如・多動性障害、錯乱状態、譫妄、健忘、失語症、精神緩慢、妄想、意識レベルの低下、幻覚、精神状態変化、神経学的代償不全、精神障害、意識変容状態、書字障害、知的能力障害
◆発現頻度
国際共同第Ⅰ/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅱ相パートにおける、ROS1融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌患者(312例)及びNTRK融合遺伝子陽性の固形癌患者(135例)の副作用発現状況、海外第Ⅰ/Ⅱ相試験(CARE試験)における25歳以下のNTRK融合遺伝子陽性の固形癌患者(19例)の中枢神経系障害の副作用発現状況は以下のとおりでした。[3]
◆発現時期
国際共同第Ⅰ/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅱ相パートにおける、ROS1融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌患者(312例)及びNTRK融合遺伝子陽性の固形癌患者(135例)の中枢神経系障害の各副作用の発現状況と初回発現までの期間は以下のとおりでした。[3]
◆予防・対処方法
電子添文上、中枢神経系障害の予防については規定されていません。[1][3]
中枢神経系障害(めまい、運動失調、認知障害等)があらわれた場合は、「休薬・減量・中止の基準」に従って、オータイロの休薬、減量又は中止を検討してください。[1][3]
NCI-CTCAE ver.4.03における中枢神経系障害のGrade別の定義については、適正使用ガイドもしくは以下をご参照ください。
日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG) 有害事象に関する共通用語規準Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 4.0(アクセス日2025年11月27日)
A オータイロの電子化された添付文書(電子添文)の警告欄では、オータイロの投与により間質性肺疾患が現れることがあると注意喚起しています。また、間質性肺疾患は重大な副作用に該当します。[1]
治療初期は、入院又はそれに準ずる管理の下で治療を開始し、間質性肺疾患の発現に十分注意してください。投与中は、初期症状(息切れ、咳嗽、発熱等)の確認や胸部CT検査等を実施するなど、十分に観察を行ってください。異常が認められた場合にはオータイロの投与を中止するなど適切な処置を行ってください。[1]
また、電子添文の特定の背景を有する患者に関する注意の項では、間質性肺疾患のある患者又はその既往歴のある患者への投与について注意喚起しています。間質性肺疾患のある患者又はその既往歴のある患者へオータイロを投与した場合、間質性肺疾患が発現又は増悪するおそれがありますので、慎重に投与してください。[1][3]
◆発現頻度
国際共同第Ⅰ/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅱ相パートにおける、ROS1融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌患者(312例)及びNTRK融合遺伝子陽性の固形癌患者(135例)の間質性肺疾患の副作用発現状況は以下のとおりでした。[3]
なお、海外第Ⅰ/Ⅱ相試験(CARE試験)における25歳以下のNTRK融合遺伝子陽性の固形癌患者(19例)では間質性肺疾患は認められませんでした1)。[3]
◆発現時期
国際共同第Ⅰ/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅱ相パートにおける、ROS1融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌患者(312例)及びNTRK融合遺伝子陽性固形癌患者(135例)の間質性肺疾患の各副作用の発現状況と初回発現までの期間は以下のとおりでした。[3]
◆予防・対処方法
電子添文上、間質性肺疾患の予防については規定されていませんが、間質性肺疾患のある患者又はその既往歴のある患者へオータイロを投与した場合、間質性肺疾患が発現又は増悪するおそれがありますので、慎重に投与してください。[1][3]
間質性肺疾患が認められた場合は、「休薬・減量・中止の基準」に従って、オータイロを中止してください。[1][3]
NCI-CTCAE ver.4.03における間質性肺疾患のGrade別の定義については、適正使用ガイドもしくは以下をご参照ください。
日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG) 有害事象に関する共通用語規準Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 4.0(アクセス日2025年11月27日)
A オータイロの電子化された添付文書(電子添文)の上、骨折は重大な副作用に該当します。[1]
オータイロの投与により、骨折のリスクを高める可能性があります。骨折は、転倒や他の損傷の有無にかかわらず起こる可能性があります。[3]
骨折の徴候及び症状(関節痛又は骨痛、可動域の変化、変形等)が認められた場合には、速やかに評価を行い、適切な処置を行ってください。[3]
また、添付文書の基準を参考に、オータイロの休薬、減量又は中止を検討してください。[1][3]
◆発現頻度
国際共同第Ⅰ/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅱ相パートにおけるROS1融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌患者(327例)及びNTRK融合遺伝子陽性の固形癌患者(135例)の有害事象発現状況、海外第Ⅰ/Ⅱ相試験(CARE試験)における25歳以下のNTRK融合遺伝子陽性の固形癌患者(19例)の有害事象発現状況は以下のとおりでした。[3]
骨折は、オータイロの投与を受けた成人患者の3.2%(TRIDENT-1試験)及び小児患者の15.8%(CARE試験)で報告されています。ほとんどの骨折はGrade 1又はGrade 2であり、主に下肢(腓骨、足等)に認められました。[3]
◆予防・対処方法
骨折の徴候及び症状(関節痛又は骨痛、可動域の変化、変形等)が認められた場合には、速やかに評価を行い、適切な処置を行ってください。[3]
また、副作用を疑う症状があらわれた場合は、「休薬・減量・中止の基準」に従って、オータイロの休薬、減量又は中止を検討してください。[1][3]
NCI-CTCAE ver.4.03における骨折のGrade別の定義については、適正使用ガイドもしくは以下をご参照ください。
日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG) 有害事象に関する共通用語規準Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 4.0(アクセス日2025年11月27日)
A オータイロの電子化された添付文書(電子添文)上、腎機能障害のある患者(非透析)への投与について制限はありません。1
オータイロの腎排泄は少なく、全投与量の約4.84%(0.56%が未変化体として)が腎から排泄されます。従って、腎排泄が主要な消失経路ではないと考えられます。[1]
また、国際共同第Ⅰ/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅱ相パートでは、クレアチニンクリアランスが40mL/分(Cockcroft-Gault式により算出)以下の患者は除外されていましたが、腎機能障害患者における薬物動態を母集団薬物動態解析により評価した結果、軽度及び中等度の腎機能障害患者における曝露量は腎機能が正常な患者と同程度であり、軽度及び中等度の腎機能障害患者に対する用量調整は必要ではないとされています。[3]
◆臨床試験における選択基準
国際共同第Ⅰ/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅱ相パートでは、ベースラインの検査値が以下の基準を満たす患者を試験に組み入れました。[3]
◆腎機能障害患者における薬物動態
オータイロの薬物動態に対する腎機能障害の影響は、母集団薬物動態解析により評価しました。eGFR-MDRD(Modification of Diet in Renal Disease)の中央値(範囲)は99.3mL/min/1.73m2(31.8~220mL/min/1.73m2)であり、腎機能は448例(69.6%)が正常(eGFR-MDRD:≧90mL/min/1.73m2)、157例(24.4%)が軽度障害(eGFR-MDRD:60~89mL/min/1.73m2)、33例(5.1%)が中等度障害(eGFR-MDRD:30~59mL/min/1.73m2)でした。腎機能障害がオータイロの薬物動態パラメータに対する有意な共変量であることは確認されず、軽度及び中等度の腎機能障害患者における曝露量は腎機能が正常な患者と同程度でした。[3]
◆薬物動態(排泄)
<外国人データ>
健康成人男性(7例)に[14C]レポトレクチニブ160mgを単回経口投与したとき、放射能の4.84%(未変化体として0.56%)が尿中に、88.8%(未変化体として50.6%)が糞中から回収されました。[1]
A オータイロの電子化された添付文書(電子添文)上、透析患者への投与について制限はありません。[1]
オータイロの腎排泄は少なく、全投与量の約4.84%(0.56%が未変化体として)が腎から排泄されます。従って、腎排泄が主要な消失経路ではないと考えられます。[1]
◆臨床試験における選択基準
国際共同第Ⅰ/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅱ相パートでは、ベースラインの検査値が以下の基準を満たす患者を試験に組み入れました。[3]
◆薬物動態(排泄)
<外国人データ>
健康成人男性(7例)に[14C]レポトレクチニブ 160mgを単回経口投与したとき、放射能の4.84%(未変化体として0.56%)が尿中に、88.8%(未変化体として50.6%)が糞中から回収されました。[1]
◆透析による除去率
該当する情報はありません。
◆血漿タンパク結合率
レポトレクチニブのin vitroにおける血漿蛋白結合率は95.4%でした。[1]
A オータイロの電子化された添付文書(電子添文)上、肝機能障害患者は投与禁忌には該当しません。[1]
しかしながら、オータイロは主に肝臓によって代謝されるため、肝機能障害はオータイロの薬物動態に影響を及ぼす可能性があります。[1][3]
中等度以上の肝機能障害のある患者(総ビリルビン値が基準値上限の1.5倍超)への投与について、電子添文の特定の背景を有する患者に関する注意の項で注意喚起しており、中等度(AST値にかかわらず、総ビリルビン値が基準値上限の1.5倍超~3倍)又は重度(AST値にかかわらず、総ビリルビン値が基準値上限の3倍超)の肝機能障害のある患者を対象とした臨床試験は実施していないため、中等度以上の肝機能障害のある患者への投与は、オータイロの有効性及び安全性を考慮して慎重に判断してください。[1][3]
なお、電子添文上、肝機能障害患者へ投与する際の用量調節について規定はありません。[1]
軽度の肝機能障害のある患者について母集団薬物動態解析において主要な薬物動態パラメータの有意な変化は認められなかったことから、用量調節は不要と考えられました。[3]
◆臨床試験における選択基準
国際共同第Ⅰ/Ⅱ相試験(TRIDENT-1試験)の第Ⅱ相パートでは、ベースラインの検査値が以下の基準を満たす患者を試験に組み入れました。[3]
◆肝機能障害患者における薬物動態
軽度の肝機能障害のある患者について、母集団薬物動態解析において主要な薬物動態パラメータの有意な変化は認められなかったことから、用量調節は不要と考えられました。[3]
◆薬物動態(代謝)
レポトレクチニブは主にCYP3A4により代謝され酸化代謝物を生成し、その後、グルクロン酸抱合を受けます。健康成人男性(7例)に[14C]レポトレクチニブ160mgを単回経口投与したとき、血漿中総放射能のAUCに対する未変化体の割合は84.3%でした。1
A 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみオータイロを投与してください。[1]
また、妊娠する可能性のある女性には、オータイロ投与中及び最終投与後2カ月間において避妊する必要性及び適切な避妊法について説明してください。[1]
経口避妊薬による避妊法の場合には、経口避妊薬以外の方法をあわせて使用するよう指導してください。オータイロは、主にCYP3A4によって代謝され、またP糖蛋白(P-gp)の基質です。また、CYP3Aに対して誘導作用を示します。オータイロの電子化された添付文書(電子添文)上、CYP3Aの基質となる経口避妊薬*は併用注意に該当します。[1]
*デソゲストレル・エチニルエストラジオール、ノルエチステロン・エチニルエストラジオール、レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール等
電子添文では、妊婦及び生殖能を有する者への投与について以下のとおり注意喚起しています。[1]
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.4 生殖能を有する者
妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び最終投与後2ヵ月間において避妊する必要性及び適切な避妊法について説明すること。経口避妊薬による避妊法の場合には、経口避妊薬以外の方法をあわせて使用するよう指導すること。
9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。動物実験(ラット)で、母集団薬物動態解析に基づく推定曝露量(160mg 1日2回)の約2.4倍に相当する投与量で胎児に奇形(後肢異常回転)及び体重の低値が認められている。
A 製品情報について検索する場合は「Medical Information library(https://www.bmsmedinfo.jp/)」をご利用ください。
製品に関して問い合わせをする場合は、「製品に関するお問い合わせ(https://www.bmsmedinfo.jp/submit-medical-inquiry.html)」ページをご利用ください。